都市銀行から融資してもらえるメリットはやはり金利が低いこと

三菱UFJ銀行。代表的な都市銀行。
今の時代、よほどの資産家でもない限り、多くのアパートオーナーは金融機関からアパートローン融資を受けてアパート経営を行っていることと思います。
そしてアパートローンを借りるならば、金利が低くしかもしっかりとした金融機関から借りたいと思うことでしょう。
そうなると候補にあがるのが都市銀行です。
この都市銀行についてコトバンクのサイトの「都市銀行」には
東京や大阪などの大都市圏に本店を置き、全国規模の業務を展開している普通銀行のこと。・・現在はみずほ銀行、三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行、りそな銀行の4大メガバンクに集約されている。
引用:都市銀行
と説明されています。
ですから地方ではあまり都市銀行の支店をみかけることはありませんが、人口が密集しているようなエリアの駅前などに都市銀行の支店をみかけることがあります。
この都市銀行からアパートローンを借りることのメリットは
①とにかく金利が低い。地方銀行やその他の銀行よりも金利が低い場合が多い。
②銀行として規模も大きいのでスケールメリット、つまりはアパートローン顧客として銀行が提供する多様化した種々のサービスを利用することができる。
といったてんをあげることができると思います。
ローンは変動金利か固定金利どちらが良い?銀行員は変動金利のほうが・・
長らく金融緩和がきましたが、調整されそうな時代になってきました。
それにしても住宅ローンになると今でも低金利な時代です。
銀行によっては変動金利のローンとなると条件次第では0%台で借りることもできます。
もちろん固定金利となると、それよりも金利は高くなります。
ところで住宅ローンにしてもアパートローンにしてもお金を借りる場合、変動金利のほうが良いか、それとも固定金利のほうが良いか、それは今も昔も迷うところです。
目先ならば変動金利のほうが低くメリットがあるわけですが、長期となると金利上昇リスクを考えて固定金利のほうが良いという方もおられます。
ところで、このてんでの銀行員による実際の声は、
これまでの経験則からすると
結果的には変動金利のほうが金利分の支払いの総額は少なくすんでいると言われます。
ですから現在の経済状況がに大きな変化がないならば変動金利で借りるほうが良いのかもしれません。
しかしもしも日本の国債が海外の投資筋によって突如売り浴びせられ、暴落するような事態が生じれば金利が急騰するリスクも考えられます。(もちろん日本全体の現在の資産状況からすると、そのような事態が生じる可能性はあまりないと考えられています)
りそな銀行からアパートローンを借りるまでのいきさつ
多くの方がアパートマンション経営を始めるさいにアパートローンを借りているのではないでしょうか。
昔はスルガ銀行のように地方銀行でありながら、全国で積極的にしかも迅速にアパートローンを貸し出している銀行もありました。
しかしスルガ銀行の場合は金利も高めで、できれば金利の低い銀行で借りたいものです。
金利が低いというとネット銀行を思い浮かべるかもしれません。
ソニー銀行とか、ジャパンネット銀行とかがありますが、残念ながら住宅ローンは扱っていてもアパートローンは扱っていないようです。
となると次に金利が低いとなると、それはメガバンクつまり都銀になります。
筆者も父の代の時から、都銀の1つりそな銀行からアパートローンを借りています。
そして確かに金利は低いです。
変動金利でアパートローンでも1%前半です。(その後の金利交渉で0%台にまで下げてもらいました)
しかし父はすんなりと、りそな銀行からアパートローンを借りることができるようになったわけではありません。
借りれるようになったいきさつについて書いていきたいと思います。
まず大東建託からアパート経営をもちかけられた時に、りそな銀行からのアパートローンの借入を検討したようですが、銀行側から手持ち資金が1000万円以上が必要などの条件がクリアできないとダメと言われ断念したようです。
賃貸併用住宅にすることのメリットしかしリスクもある
銀行のローンの種類は様々でも住宅ローンが金利面などで最も優遇されている事は既知の事実です。
ところでアパートマンションの建設費用のための融資ないしはローンは基本的にはアパートローン、つまりは事業性ローンとなります。
よって金利は住宅ローンよりもやや高くなります。
そしてアパートローンなどの億円前後のローンになると金利が少し上下するだけで、支払う利息額も大きく違ってきます。
例えば1億円のローンを組むとします。
30年返済、元利均等方式の場合、金利が1.5%の場合、利息の支払い総額は¥2424万3068円です。
一方で同条件で、金利が0.8%の場合、利息の支払い総額は¥1251万2523円となります。
つまりは金利が0.7%違うだけで利息支払い額が約1200万円ほど違ってくるのです。
となると住宅ローンのほうが、有利なのは間違いありません。
1200万円となると小規模なマンションの大規模改修工事に、おそらくは十分に足りるだけの金額です。
このてんで打つ手はあるのでしょうか。
実はこのてんで、ある程度は打つ手があります。
アパートマンション建設の場合でも住宅ローンにする方法があるのです。
店舗のないネット銀行のメリットはなんといってもローン金利が低い
昔は住宅ローンを借りるさいには、どの銀行から選ぶかとなると、まず最初に都市銀行、都市銀行がダメだったら次に地方銀行、地方銀行がダメだったら次に信用金庫といった法則のようなものがありました。
つまりはローン金利の低い順番であたっていくというのです。
しかし最近はその法則がに変化が生じているようです。
というのも基本的に店舗も通帳もない
ネット銀行の金利が最も低い
というケースが多くなっているのです。
多くの方が、インターネットをあたりまえのように活用している現代、ネット銀行、ネット証券そしてネット保険を活用する方も多くなってきました。
これらの金融機関の特徴は、店舗がないために事業にかかるコストが低く抑えることができるために、ローン金利を低く抑えることができますし、そして種々の手数料も安く抑えることができるといったメリットがあります。
またネット保険の場合は毎月支払う保険料を安く抑えることができるというメリットもあることでしょう。
都市銀行の一つりそな銀行の筆者の担当者も住宅ローンの金利においては、「ネット銀行にはかなわない」ということを言っておられ、ネット銀行に客をもっていかれることへの危機感を持っておられました。
このようにどうしても生活上のコストを抑えたい場合はネット銀行を活用することには大きなメリットがあります。
銀行からのローン返済予定表は経費計上のための大切な書類
昨年もアパートローンを借りている、りそな銀行からローン返済予定表の手紙が送られてきました。
差出人はりそな銀行の担当支店になっているので、担当の支店で金利などが決められているのかと思いきや、りそな銀行支店の担当者の話では「支店ではなく本部の融資の部署で作成されている」と言われていました。
つまりはローン金利などの重要事項は支店では決めることができず、すべて本部で決められているということなのでしょう。
ところで変動金利の場合は金利の見直しは4月1日と10月1日に行われます。
今回は10月1日に見直しが行われた分で翌年の1月から6月までの金利が示されています。(4月1日の見直し分は7月から12月の金利となります)
りそな銀行のインターネットバンキングでは、いち早く1月から6月までの金利を知ることができますので、もうすでに金利を知ってはいましたが、手紙で送られた分もやはり同じ金利でした。
当然といえば当然のことですが。
そして今回は変動金利の金利は上がりました。
近年は変動金利もずっと同じ水準を保っていたのですが・・
金利が非常に低い住宅金融支援機構 しかしデメリットも!!
以前のことですが大東建託支店の営業担当の方が来られた時に、恥ずかしながら初めて知ったのですが、住宅金融支援機構から賃貸住宅のための資金を借りることができることを知りました。
住宅金融支援機構といえばフラット35といった商品で聞いたことはありましたが、35年固定金利でしかも民間の金融機関よりも、かなり低い金利で借りられるといったことは知っていましたが、個人の住宅ローンのみを対象にしているものと思っていました。
しかも半分民間、半分公的な機関で、弱者救済的な機関といったイメージがありましたので、賃貸住宅とは無縁な機関だと思い込んでいました。
それが大東建託の営業担当の話によると、アパート建設のための資金も住宅金融支援機構から借りることができるというのです。
しかも大東オーナーさんの多くも実際のところ住宅金融支援機構から、お金を借りてアパート経営をやっているというのです。
ところでこの住宅金融支援機構からお金を借りるメリットは何でしょうか。
それはなんといっても
都銀よりも低い金利です。
例えば2018年9月では35年固定金利が、1.5%台になっています。
もちろんそれでも都銀などから変動金利でアパートローンを借りているならば1%台前半や、それ以下の金利で借りている方もおられるかもしれませんが、固定金利になると当然金利は上がります。
銀行のほうからローン金利を下げてくれることはまずありえない
以前に大東建託の営業の方との、お話をしていた時に、銀行のローン金利の話になりました。
その時に営業の方が「絶対に銀行から金利を下げるといったことは言わないから、自分のほうから金利交渉をもちかけてください」とアドバイスしてくださいました。
そこで、今度、銀行の担当者に会った時に金利交渉の話をしてみようと心に決めていました。
実は2年前にも金利交渉をして、少し金利を下げてもらったことが、あったのですが、もう一度ダメモトで挑戦してみようと思っていたのです。
そこで、他の用事で、銀行の担当者が来られた時に、思い切って話を切り出しました。
すると担当者は「そうですね。最近は住宅ローン金利も驚くほど低くなってますしね。検討してみます」と言われて帰られたのですが、それから1時間ほどして、担当者から電話がかかり「金利の話をされましたが、そのことで支店長と一緒に訪問したい」とのこと。
それから数日後に、支店長と担当者が来られました。
ひょっとしたらお断りのために訪問してこられたのかとも思いましたが、支店長が話を切り出され「優遇金利幅を0.2%拡大させていただきます」とのこと。
どうやら今回も金利交渉で金利下げを受入れてくださったようです。
生じると言われながら生じない日本国債の暴落 なぜ?
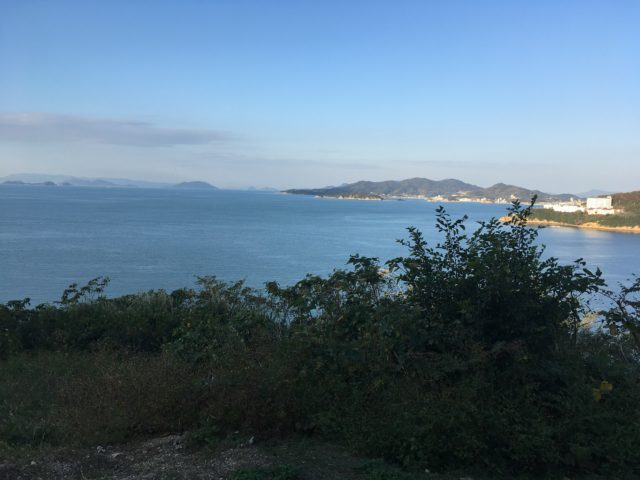
賃貸住宅オーナーがアパートローンなどを借りているならば、気になることは金利です。
とくに変動金利で借りているならば、金利の上昇に神経を尖らせていることでしょう。
そして金利上昇リスクの要因の1つに国債の暴落があります。
日本は国債大国で、万が一その国債が暴落すれば金利は急騰します。
そして近年、国債残高が右肩上がりで増加し、いずれは国債が暴落しそれに伴い金利が急騰するという意見が聞かれるようになりました。
ある人気番組の劇場版でしたか、国債暴落のXデーを仮定した映画も見ましたが、そういう映画を見ると本当に将来、国債が暴落するのではないかと考えてしまいます。
特にアパートローンを変動金利で借りていると国債暴落、金利急騰のシナリオは最悪のシナリオの1つです。
では本当に国債は暴落するのでしょうか。
あれから数年たちましたが、現実は国債は暴落してません。
ところで
日本全体の純資産は少なくとも2000兆円はある
とも言われています。
国債が投げ売りされない理由の1つは日本の土地、株、預貯金等のすべての純資産が少なくとも2000兆円はあるといてんにあります。
つまり1000兆円という膨大な借金があっても2000兆円という、しっかりとした担保資産があるのです。
また国債の多くは日本銀行が所有しています。
さらに国債の保有先ですが日本銀行の数十%以上をはじめ、国民年金資金、ゆうちょ銀行など公的色彩の強い機関が多くの国債を保有しています。
これらの公的な機関が投げ売りすることは考えにくいことです。
結論として、国際暴落そして金利急騰は当分は起こり得ないということになります。
しかし将来的には懸念すべきことがあります。
その1つは地価が年々下落しているというのです。
数年前までは1000兆円あったのが現在は850兆円程度まで下がっています。
つまり担保資産が目減りしているのです。
思い切った地価対策を政策的に行う必要があるように感じます。
もう1つの懸念事項は国債には償還期限があり、償還資金は基本的には税金で賄われているというてんです。
日銀などの公的機関は償還日が来ても継続して国債を保有することができますが、民間機関の保有の場合、どうしても換金したい場合に支払わなければなりません。
この場合は増税して換金資金を賄うのか、さらに国債を増発するのかという選択に迫られます。
いずれにしても国債暴落は起きないにしても異常な国債残高はいずれ、いずれどこかで帳尻を合わせなくてはならないということなのかもしれません。
追記:なぜか一時期は国債暴落のうわさが話題になっていましたが、今なぜかその話題が下火になっています。
日本の国債が、実際のところ暴落しにくいということに、多くの方が気づいてきたからでしょうか。
今でも、日本の国債は安全資産とみなされ、アメリカドルと並んで、市場が不安定な時は日本国債は買われています。
考えてみると、日本国債が万が一、投げ売られても日本銀行が、日本円で日本国債を買い支えることによって、日本国債の暴落を防ぐことができます。
ただし、その時のリスクは、日本円の市場価値が下がって、極度の円安になり、悪質なインフレが発生することです。
その時には、金利上昇を許容することによって、極度の円安やインフレを防がざるをえなくなるかもしれません。
ただ上記でも書きましたように、日本国債を大量に保有しているのは、日本銀行をはじめとする公的な機関ですし、日本の銀行や保険会社も多く保有しています。
それで公的な機関が国債を投げ売りすることは考えられませんし、国債価格が急落する場合には、日本政府が銀行や保険会社に国債を投げ売りしないように働きかけることも考えられます。
海外のヘッジファンドや機関投資家の保有比率に注意をしているならば、さほど心配することがないのかもしれません。
銀行の借り換えには多額の費用がかかる しかし長期的には・・
住宅ローンでもアパートローンでも、借りている銀行を換えることができます。
一般に借り換えといいますが、よく知られている借り換えのパターンとしては、住宅ローンを当初は地元の信用金庫から借りていたのを、数年後には地方銀行か都市銀行に換えるというケースです。
結果として利息支払い分がかなり安くなったというパターンです。
昔からお金を借りる時の原則は最初は都市銀行にあたり、ダメだったら次に地方銀行にあたり、地方銀行もダメだったら信用金庫という順番であたるという原則があります。
つまりは金利の低い金融機関から順番にあたっていけということなのです。
筆者の父もマンション経営を始めたころは、都市銀行も相手にしてもらえず、結局は外資系のノンバンクのようなところで借りはじめたのが、最初です。
それから5年ぐらい経過したのちに、ある都銀から借り換えの勧誘を受け、借り換えの審査を受けることに。
最初の審査は2次審査で落とされましたが、1年後にもう一度トライし、今度は合格しようやく都市銀行から借り入れることができるようになりました。
結果として利息支払い分が年間100万円ほど圧縮することができるようになったのです。



